官公庁などの文書は「です・ます」と「だ・である」どちらを望むか
2019/11/02 05:18
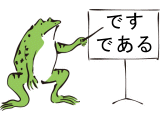 文化庁は2019年10月29日、平成30年度分の「国語に関する世論調査」の結果を発表した。今発表内容は概要ではあるが、日本の国語の理解や意識の現状を確認できる、興味深いデータが多数盛り込まれている。今回はその中から、官公庁などが示す公用文において用いる文体は、「です・ます」体と「だ・である」体のどちらが望まれているかについて確認していくことにする(【平成30年度「国語に関する世論調査」の結果について】)。
文化庁は2019年10月29日、平成30年度分の「国語に関する世論調査」の結果を発表した。今発表内容は概要ではあるが、日本の国語の理解や意識の現状を確認できる、興味深いデータが多数盛り込まれている。今回はその中から、官公庁などが示す公用文において用いる文体は、「です・ます」体と「だ・である」体のどちらが望まれているかについて確認していくことにする(【平成30年度「国語に関する世論調査」の結果について】)。スポンサードリンク
今調査は2019年2-3月に全国16歳以上の男女に対して個別面接調査方式で行われたもので、有効回答数は1960人。調査対象の抽出方式や属性別構成比は非公開。
次に示すのは官公庁などが示す文書のような公文書を読む場合、「です・ます」体と「だ・である」体とどちらがよいかを尋ねた結果。単純に回答者にとってどちらがよいか・望むかを答えてもらったものであり、法的な縛りなどの話ではない。あくまでも回答者が公文書の文体はどちらが望ましいと考えているかについて。
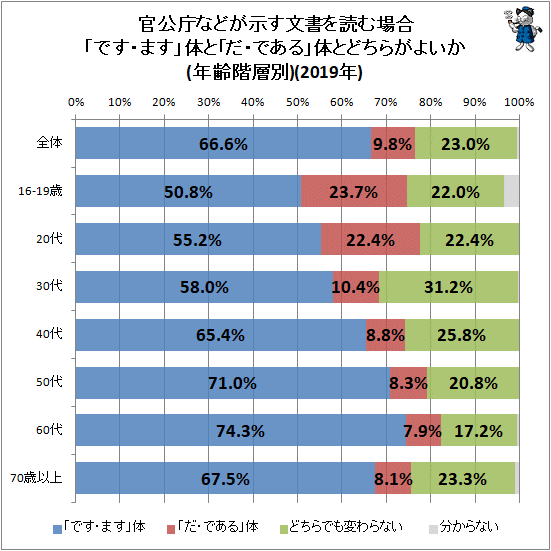
↑ 官公庁などが示す文書を読む場合「です・ます」体と「だ・である」体とどちらがよいか(年齢階層別)(2019年)
全体では66.6%が「です・ます」体を望み、「だ・である」体を望んでいるのは9.8%に留まっている。どちらでも印象は変わらないとする意見は23.0%。圧倒的に「です・ます」体が望まれている。公用文では現状においては全般的に「です・ます」体が使われることが多く、不特定多数に公知する必要があるパンフレットなどでは特にその傾向が強い。他方、研究発表的な報告書や公開前提の会議の資料などでは「だ・である」体が多い。「です・ます」体の方が印象として丁寧な感を持ちやすいため、読みやすさのハードルも低くなるとの思惑があるのだろう。
一方で年齢階層別の動向を見ると、「です・ます」体の方が多数派で過半数なのはどの年齢階層でも変わらないものの、若年層の方が「だ・である」体の方を好むとの意見が多い。高齢者の方が公用文は丁寧であるべきだというような定説的ルールを強く望んでいるようだ。あるいはお役所が強い文体で公知をすることへの反発心のようなものが、高齢者には強いのだろうか。60代では実に3/4近くが「です・ます」体を望んでいる。
今主流の「です・ます」体から「だ・である」体へ変えた場合、丁寧でなくなった、高飛車に読める、失礼だなどとのクレームが寄せられるリスクを考えると、今後も公用文などでは「です・ます」体が使われることに違いはない。もっとも、偉そうにしたいから「だ・である」体が使われるわけではないので、本来ならばどちらでもよいはずのではあるのだが。
■関連記事:
【一緒に仕事をした相手、終わった後の謝意の言葉は「お疲れ様」か「ご苦労様」それとも「ありがとう」か】
【子供の言葉遣いに影響を与えそうなもの、トップはやはりテレビ】
【日々の生活を勇気づける7つの言葉】
スポンサードリンク
関連記事
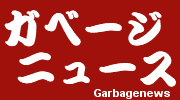
 最新情報をRSSで購読
最新情報をRSSで購読