日本の携帯電話契約者数動向をまとめてみる(2013年8月末まで)
2013/09/07 15:00
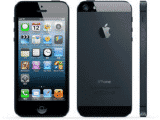 先日【純増数はSBMとauの二強状態続く、ドコモはかろうじてプラス(2013年8月末携帯電話契約数)】でも解説したが、昨今の日本国内における携帯電話契約者数動向は、三強企業のうちauとソフトバンクモバイル(SBM)が数を順調に伸ばす一方、NTTドコモは今一つ伸び悩みを見せ、MNP(Mobile Number Portability。ナンバーポータビリティ。電話番号を継続しつつ契約会社=キャリアを変更できる仕組み)でもドコモは他の二社への移転者数が多い状態が続いている。そのような中で「今月10日に行われるとされるアップルの新商品発表会をきっかけに、ドコモもiPhoneの発売を始めるのではないか」とする話が複数ルートで伝えられる状況が生じている。国内携帯電話市場ではiPhoneの販売が大きなカギを握っていることもあり、この話が事実であれば、今後市場では小さからぬ動きが生じ得る。そこで今回は良い機会でもあり、当サイトでこれまで継続解説してきた携帯電話契約数の各種データを整理し、一部のグラフを再構築して状況をまとめることにした。
先日【純増数はSBMとauの二強状態続く、ドコモはかろうじてプラス(2013年8月末携帯電話契約数)】でも解説したが、昨今の日本国内における携帯電話契約者数動向は、三強企業のうちauとソフトバンクモバイル(SBM)が数を順調に伸ばす一方、NTTドコモは今一つ伸び悩みを見せ、MNP(Mobile Number Portability。ナンバーポータビリティ。電話番号を継続しつつ契約会社=キャリアを変更できる仕組み)でもドコモは他の二社への移転者数が多い状態が続いている。そのような中で「今月10日に行われるとされるアップルの新商品発表会をきっかけに、ドコモもiPhoneの発売を始めるのではないか」とする話が複数ルートで伝えられる状況が生じている。国内携帯電話市場ではiPhoneの販売が大きなカギを握っていることもあり、この話が事実であれば、今後市場では小さからぬ動きが生じ得る。そこで今回は良い機会でもあり、当サイトでこれまで継続解説してきた携帯電話契約数の各種データを整理し、一部のグラフを再構築して状況をまとめることにした。スポンサードリンク
契約者数増減動向とiPhoneの販売との関係
まず最初は、主要三社における携帯電話契約件数の増減を折れ線グラフにし、その上で国内のiPhone販売動向の主な出来事を加えたもの。
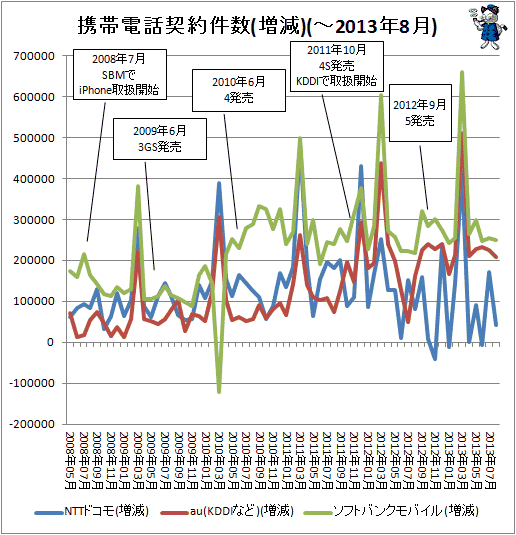
↑ 携帯電話契約件数(増減)(-2013年8月)
iPhone4が発売された2010年6月頃からSBMの飛躍が始まる一方、ドコモとauがそれに後れを取る形で両社横並びで追随。そして1年強の後にau(KDDI)もiPhone 4Sから販売を始めるようになり、ドコモとの横並びからSBMの背中を追いかける形に移行しているのが分かる。ほぼそれと時を同じくして、ドコモは増減数の上で低迷を始め、前月比で純減を繰り返すようになる。
他にも理由はいくつか考えられるし、契約総数はまだまだドコモの方が上ではあるが、月次純増数の動向の上ではiPhoneの販売の是非が少なからず関係していることは容易に想像できる。
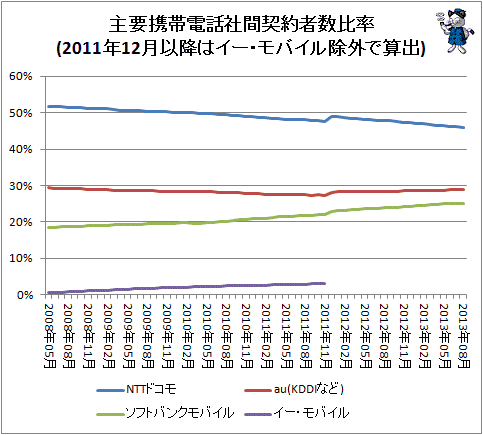
↑ 主要携帯電話社間契約者数比率(2011年12月以降はイー・モバイル除外で算出)
一般携帯電話(フィーチャーフォン)時代の蓄積があり、契約総数では未だドコモが最大数を示しているが、過半数は2010年3月を最後に割り込んだままで、直近の2013年8月時点では3者間合計に対するドコモの比率は46.0%にまで落ち込んでいる。契約数そのものは漸増しているが、他の2社の増加数の方が多いので、相対的にシェアが縮小してしまっているのが現状。しかもその状況は今なお継続中である。
「iPhoneがポイント」がさらに良くわかるMNPの動向
上記のグラフは月次の契約者総数の増減だが、次に示すのはMNPの推移。やはり当サイトで記事展開を始め、データを収集しはじめた2008年5月からのものだが、iPhone発売に絡んだ主要動向をかぶせてみると、各社のMNP変動の理由が良くわかる。

↑ MNP件数推移(-2013年8月)
iPhoneの展開前からドコモはMNP制度の上では軟調、分かりやすく表現すれば「お得意様が他企業に移転してしまう」状態だった。auはSBMとドコモの板挟み的な雰囲気で、プラスとマイナスを行き来。SBMは概して堅調だが、移入数はさほど多くは無かった。
それが上記の純減増グラフでも解説している通り、iPhone4の発売をきっかけに、状況が大きく変化する。SBMは移入者数が大いに増加する一方、auとドコモはマイナス常連となる。シンプルに表現すれば「ドコモとauからSBM(のiPhone)に利用客が移転する」ような状態。
これが2011年10月に、auもiPhoneの販売を始めることで状況は一転する。SBMへの移入者数はやや抑え気味となり、auは一挙にマイナスから浮上しプラスの常連に。しかもSBMを抜いてMNP増加数ではトップを維持するようになる。他方ドコモはSBMだけでなくauへも「iPhoneを求めてMNPを使った移転組」が移行するようになり、減少幅は拡大する。そして今なお、その拡大傾向は継続中である。
もし仮に……なら?
契約者数の純減増にしても、MNPの増減にしても、iPhoneの販売動向がすべてを握っているわけではない。料金サービス体系、サポート動向、通信環境の良し悪し、そしてiPhone以外の多種多様な新機種の展開が、少なからぬ影響を与えている。
とはいえ、日本では海外以上にiPhoneが一種のブランドと化して絶対視されていることや、実際の販売普及動向、そして今回挙げた複数の数字の変移とiPhone関連の事象とのタイミングの一致性を見るに、大きな要因であることには違いない。
 仮に噂通りドコモがiPhoneの販売を始めるとしても、SIMロックや料金体系、通信環境の問題など、気になる点は多い。これらの点については多数の専門家諸氏による分析がなされるだろう。しかし多くの携帯電話ユーザーにしてみれば、そこまで深く考えるまでには至らず、単に「ドコモでもiPhoneを出すのね、ならばMNPを使わずに済むな」「キャリアを気にせずiPhoneを選択できるね」という認識に至るものと考えられる。またドコモにしてみれば、MNPによる流出者の少なからずがauやSBMのiPhone目当ての可能性が高いことから、流出を抑える効果が期待できる。
仮に噂通りドコモがiPhoneの販売を始めるとしても、SIMロックや料金体系、通信環境の問題など、気になる点は多い。これらの点については多数の専門家諸氏による分析がなされるだろう。しかし多くの携帯電話ユーザーにしてみれば、そこまで深く考えるまでには至らず、単に「ドコモでもiPhoneを出すのね、ならばMNPを使わずに済むな」「キャリアを気にせずiPhoneを選択できるね」という認識に至るものと考えられる。またドコモにしてみれば、MNPによる流出者の少なからずがauやSBMのiPhone目当ての可能性が高いことから、流出を抑える効果が期待できる。噂が事実か否かは、10日以降に明らかになる。現実のものとなれば、日本の携帯電話市場(、そして国産の携帯電話開発・製造メーカーにも)に小さからぬインパクトを与えることは間違いあるまい。
■関連記事:
【四半期単独販売数で初めてスマホが過半数…世界全体のスマートフォンや一般携帯の販売動向(2013年第2四半期まで版)】
スポンサードリンク
関連記事
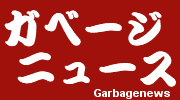
 最新情報をRSSで購読
最新情報をRSSで購読