家庭内外で最もよく使うネット接続機器(2011年分反映版)
2012/06/24 06:50
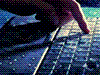 総務省は2012年5月30日、平成23年(2011年)調査における通信利用動向調査を発表した(【発表ページ】)。日本におけるインターネットや携帯電話など、情報通信関連の各種調査結果を反映した調査結果で、毎年7月頃に発表される【情報通信白書】のベースにもなる、同省の情報通信統計としては非常に重要なものである。現時点では概要、及び統計データのe-Statへの収録のみで報告書の類は完成していないが、今回はそのデータから「家庭内と家庭外でもっともよく使う、インターネット接続のための機器の分布状況」をグラフ化してみることにする。
総務省は2012年5月30日、平成23年(2011年)調査における通信利用動向調査を発表した(【発表ページ】)。日本におけるインターネットや携帯電話など、情報通信関連の各種調査結果を反映した調査結果で、毎年7月頃に発表される【情報通信白書】のベースにもなる、同省の情報通信統計としては非常に重要なものである。現時点では概要、及び統計データのe-Statへの収録のみで報告書の類は完成していないが、今回はそのデータから「家庭内と家庭外でもっともよく使う、インターネット接続のための機器の分布状況」をグラフ化してみることにする。スポンサードリンク
今調査(通信利用動向調査)は2012年1月-2月に、地域及び都市規模を層化基準とした層化二段抽出方式による無作為抽出で選ばれた、20歳以上の世帯主がいる世帯・構成員4万0592世帯に対して行われたもの。有効回答数は1万6580世帯・4万7158人(企業に対して行われたものは常用雇用者規模100人以上5140企業/有効回答数1905企業)。調査方法は郵送による調査票の配布および回収なので、各媒体の保有率は調査結果に影響を与えていない。
先に【インターネット普及率の推移(2011年分反映版)】で示した通り、インターネット普及率は8割近くにまで及んでいる。
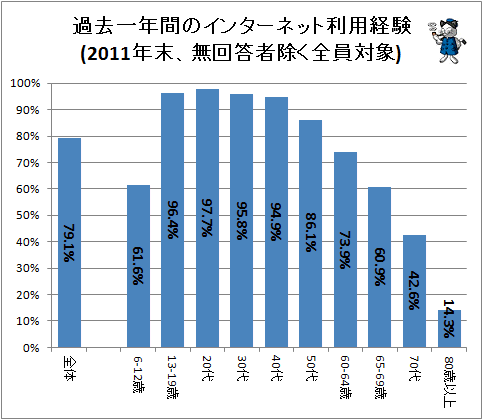
↑ 過去一年間のインターネット利用経験(2011年末、無回答者除く全員対象)
インターネットにアクセスする際には一つ、あるいはそれ以上の機器を窓口にする。例えばパソコン、例えば携帯電話、例えばゲーム機。それらの中で、自宅の中・自宅の外それぞれにおける「もっともよく使っている」機器を聞いたのが今回の調査結果項目。まずは家庭内だが、自宅のパソコン(PC)と答える人がもっとも多く、全体では3/4。次いで一般携帯電話が16.2%という形となった。
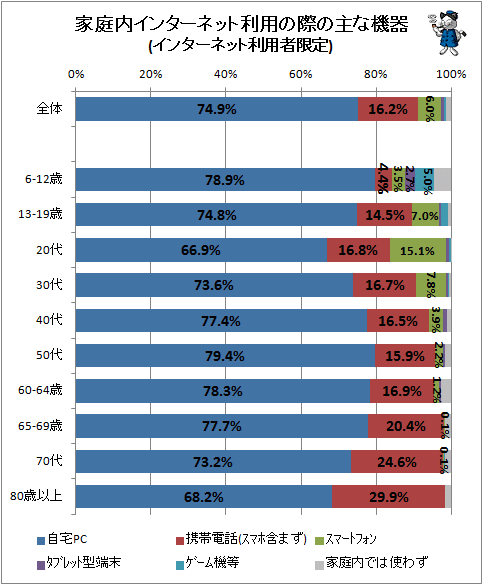
↑ 家庭内インターネット利用の際の主な機器(インターネット利用者限定)
複数のアクセス機器を所有していても、使える状況下なら、より便利な機器を使うもの。ノート、あるいはデスクトップいずれにしても、パソコンを使う人がもっとも多いのは道理が通る。
一方で携帯電話を使う人も案外多い。特に60代を超えるとその割合は増加し、70代以降は1/4を超える。これは以前【インターネット機器としての個人の携帯電話やパソコン利用率(2011年分反映版)】などでも触れた通り、「パソコンは難しいしコストがかかる」「スマートフォンは操作性の問題がある」などの観点から、高齢者が一般携帯電話を愛用している事例が多いことを裏付けている。
他方20代では一般携帯電話とスマートフォンが競っているのも確認できる。「家庭内でのインターネット利用で最多利用端末」の3割強がモバイル系端末というのも驚きだが、そのうち約半数がスマートフォンである事実も、昨今のデジタル機器の動向を再確認させる値といえる。
これが家庭外となると、状況が一変する。
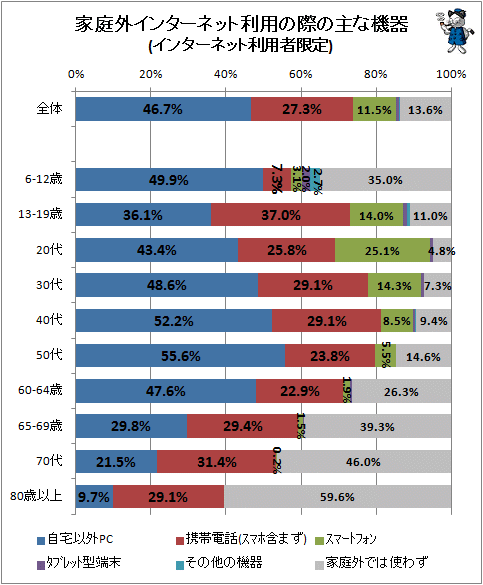
↑ 家庭外インターネット利用の際の主な機器(インターネット利用者限定)
全体の半数近くは自宅外のパソコン。例えば学校の教材や会社での端末を意味するが、それらを使ってネットにアクセスする時間がもっとも長いということ。幼少時は学校の端末を用い、就職して歳を経るごとに会社でのパソコン利用時間が長くなり、回答者も増える次第(同時に壮年者ほどモバイル端末に触れる機会が少ないのも、会社での端末利用が「一番」となる理由でもある)。
 気になる動きを2点ほど。双方とも「家庭内」と同じ着目点ではあるが、まず1点目として高齢者は半数前後が「家庭外では使わず」と答えている。そしてパソコンと同等かパソコン以上に一般携帯電話を使う事例が一番と回答している。会社や学校に足を運ぶ機会がないためであり(再就職をしていれば話は別だが)、当然といえば当然の話。
気になる動きを2点ほど。双方とも「家庭内」と同じ着目点ではあるが、まず1点目として高齢者は半数前後が「家庭外では使わず」と答えている。そしてパソコンと同等かパソコン以上に一般携帯電話を使う事例が一番と回答している。会社や学校に足を運ぶ機会がないためであり(再就職をしていれば話は別だが)、当然といえば当然の話。もう1点は若年層、特に20代。会社や学校でのパソコン利用以上に、モバイル系端末、特にスマートフォンの利用率が他世代と比べ目立って多い。インターネットを使っている20代の4人に1人は「家の外のネットアクセスは、スマートフォン経由が一番多い」と答えていることになる。
今後スマートフォンの普及が拡大するにつれ、20代に見られる傾向が30-40代にまで拡大していくことは、容易に想像できる。一方で高齢者の動向がどのように変異するのか、気になるところではある。
やや余談になるが。内外合わせてタブレット型端末の回答率は事実上ゼロに等しく、6-12歳でわずかに数%がみられる程度。普及数・率そのものがまだ少ない以上、他の端末と比べて「1番」になる事例が少ないのも当然の話。
【スマホとタブレット、双方ともパソコンと併用傾向強し・タブレットはスマートフォンとも】にもあるように併用される事例が多いこと、スマートフォンほど機動力は高くなく、利用範囲としては(ノート)パソコンに近いことを考えると、今後も「1番」使われる事例はさほど増えることはないのかもしれない。
スポンサードリンク
関連記事
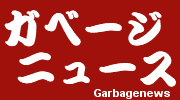
 最新情報をRSSで購読
最新情報をRSSで購読