小学一年生(2010年8月号・とびだす小一! 3D大特集号)
2010/07/10 19:00
 「Garbage Shot」第百三十五回。今回は先に【最新号の小学一年生が3D野郎で凄いらしい】で紹介した、小学館の子供向け教育誌『小学一年生の2010年8月号』。「何をいきなりそんな子供向け雑誌を」とツッコミが入るだろう。理由はといえば、平面描写の写真や動画を3Dに見せる技術を、2つの仕組みから実践できる付録がついているとの紹介記事を目にし、思わず購入した次第。【3D映画の専用メガネ、使ってみてどうでした? 45.9%もの人が……】などにもあるように、3Dテレビやゲームが話題に登る機会が多いために組まれた特集と思われるが、その中身はいかに。
「Garbage Shot」第百三十五回。今回は先に【最新号の小学一年生が3D野郎で凄いらしい】で紹介した、小学館の子供向け教育誌『小学一年生の2010年8月号』。「何をいきなりそんな子供向け雑誌を」とツッコミが入るだろう。理由はといえば、平面描写の写真や動画を3Dに見せる技術を、2つの仕組みから実践できる付録がついているとの紹介記事を目にし、思わず購入した次第。【3D映画の専用メガネ、使ってみてどうでした? 45.9%もの人が……】などにもあるように、3Dテレビやゲームが話題に登る機会が多いために組まれた特集と思われるが、その中身はいかに。スポンサードリンク
届いた「小学一年生の2010年8月号」の封を開け、早速中身を取り出してみる。ポケモンの「まいにちドリル」やドラえもんの「漢字1006の本」と共に、お目当ての「赤青3D定規」、そして組み立て式の「3D立体シアター」が目に留まる。

↑ 「小学一年生の2010年8月号」の本誌と中身一覧
まず気になったのが、くの字型に変形できる「赤青3D定規」。赤と青それぞれ7.5センチの長さを有しており、まっすぐに伸ばすことで15センチの定規として利用できる。目に当てて利用する時は、自分の目の位置にうまく「右目が青」「左目が赤」になるように折り曲げて調整。

↑ 「赤青3D定規」で見ると浮かび上がって見えるページ。
これは数々の3D映画で使われる「赤と青のセロファンで創られた紙製の眼鏡」や専用の貸し出し用眼鏡で見れるタイプの3D方式で、「アナグリフ式」と呼ぶのだそうな。そして使われている写真の撮影と加工はその道のプロである【関谷隆司氏】が担当しているとのこと。
該当号には上の写真にあるビル街の他に東京ドーム、山手線、東京スカイツリー、そして花火など、さまざまな3D用写真が掲載されており、「赤青3D定規」を介して立体視で楽しむことができる。記事上の写真ではその「盛り上がり具合」を表現できないのが残念。

↑ 子供が興味を持ちそうな、新幹線の路線安全確認車両「ドクターイエロー」の写真もある。
もう一つの立体視用の付録は3Dビューア「3D立体シアター」。こちらはレンズをセロテープで貼り付け、簡単な工作をすることで完成。3Dに見える仕組みは「ステレオ平行法・ビューア式」(右眼で右の画像、左眼で左の画像を見るやり方)とのこと。

↑ 本誌の説明に従って製作。カッターなどは必要なし。10分もあれば完成する。
「3D立体シアター」は付録の「3D立体ブック」に固定し(挟みこむ場所が用意してある)、掲載されている2枚の写真をビューア越しに同時に眺めることで立体視できる。こちらも写真でその立体感が表現できなくて残念至極。


↑ 「3D立体ブック」のコアラを見てみる。ビューア越しでないと同じ写真が二枚横並びになっているようにしか見えないが……。
嬉しいのは今回の3D関連の2つの付録双方が、今号の掲載写真だけに限定されたアイテムではないこと。【アナグリフ式】も【ステレオ平行法】も非常にメジャーな立体視(写真)の方法で、インターネット上で検索すれば(それぞれの形式名を検索キーワードにすればOK)多数の写真や動画を見つけることができる。それらの素材に対しても(「3D立体シアター」は利用するのに少々工夫がいるが)、十分使えるツールになる。
↑ 江ノ島水族館のようすを「アナグリフ式」で動画にしたもの。
さらに「3D立体ブック」の後半部分には、写真作成の関谷隆司氏のサイトを紹介し、自分自身でもパソコンを使って「アナグリフ式」や「ステレオ平行法」の写真を作る方法まで指南している。
上の動画にもあるが、実は「立体視」に関しては得意な人・苦手な人がいる。左右で視力に違いがある人、片方の目だけでモノを見る癖がついている人は苦手な場合が多いといわれているが、実は当方も「苦手な人」の一人。裸眼ではほとんど立体視ができず、紹介記事を見ても「何でこれが立体視できるの?」と首をかしげることばかりだった。
今回の付録で色々と試したところ、それなりに立体視を体感できて大満足。とりわけ「アナグリフ式」の定規は小さく折り畳んで持ち運べるため、色々と活用ができそうだ。……ただ、やっぱり長時間使用すると、目が疲れるのも確か。その点にはご注意を。
ともあれ、3Dに興味がある人は、是非一度トライしてほしい。
■関連・参考記事:
【3D映画の専用メガネ、使ってみてどうでした? 45.9%もの人が……】
【3D野郎マストバイ!今月の『小学一年生』がスゴい(MobileHackerz:外部サイト)】
スポンサードリンク
関連記事
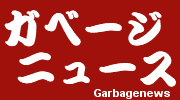
 最新情報をRSSで購読
最新情報をRSSで購読